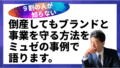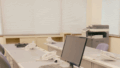2024年4月から、相続登記が義務化されました。これは、所有者不明土地問題を解消するための大改革です。登記がなされず、名義が故人のまま放置されている不動産について、法律で相続登記を義務づけることによって、土地の流通や管理を円滑にしようという目的です。
しかし、この法律の衝撃的なポイントは、「過去の相続にも遡って適用される」という点です。
私自身、弁護士として制度改正については把握していたつもりでしたが、制度開始以前の相続についても登記義務が生じると知ったときは、正直驚きました。そして、これが実務に与える影響の大きさに、事業再生や倒産案件を数多く扱ってきた立場として、警鐘を鳴らさずにはいられません。
放置されている「負動産」──誰もが関係者になる時代
現在、日本全国には、相続登記がされていない土地・建物が無数に存在します。なかでも地方の山林や原野、雑木林など、利用価値の低い、あるいは事実上ゼロの不動産が放置されているケースは後を絶ちません。これらは、俗に「負動産」とも呼ばれ、所有すること自体がマイナス資産となり得ます。
買い手も借り手もなく、固定資産税や管理責任だけがのしかかる。登記上は既に亡くなった方が所有者であり、相続人同士でも話し合いがつかず、押し付け合いになっている。そんな現実が、地方だけでなく都市部の周縁地域でも散見されます。
しかし、法律はこのような「価値がない」「使えない」「いらない」不動産であっても、相続登記を義務づけます。

義務の内容と罰則──令和9年までの猶予に潜むリスク
義務化のポイントは以下の通りです:
- 相続登記は、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。
- 既に相続が発生している「過去の相続」にも遡って適用されます。
- 正当な理由なく登記をしない場合、10万円以下の過料(行政罰)を科される可能性があります。
- 経過措置として、令和9年(2027年)3月31日までに過去の相続分を登記すれば、過料の対象外とされます。
つまり、既に親や祖父母が亡くなって久しいという方でも、放置している不動産があれば、令和9年の期限までに登記手続を行わなければならないのです。
「担保不動産」と相続登記──事業再生現場で直面する矛盾
私が関与してきた事業再生や倒産案件では、「相続されていない担保不動産」という問題が繰り返し現れます。たとえば、企業経営者が死亡し、所有していた土地や建物が金融機関の担保に入っていた場合、相続人はその不動産を「価値のないもの」「負債の延長」と捉え、手続を取らずに放置する傾向があります。
また、金融機関側も、担保価値が著しく下がっているとき、回収コストを考慮して競売等を回避することが少なくありません。こうして、担保が放置され、名義は故人のまま、相続登記もなされないという悪循環が生じるのです。
しかし、法改正後は、こうした「誰も動かない不動産」であっても、相続人が登記義務を果たさなければなりません。仮に担保に入っていたとしても、「誰かのもの」である限り、義務は課されます。金融機関が動かなくても、相続人が動かなければ過料のリスクは現実のものとなります。
今、何をすべきか──相談と準備が不可欠
この制度改正によって最も困るのは、「制度を知らなかった」「不動産に価値がないから放っておいた」という人たちです。実際、私の周囲でもこの制度について十分に理解していない方がほとんどです。
特に中小企業の経営者にとって、会社と個人の財産が複雑に絡み合っていることも少なくありません。個人名義の不動産が事業の担保となっていたり、家族が知らぬ間に登記や債務保証がなされているというケースもあります。そうしたケースこそ、早期に状況を洗い出し、専門家と共に整理することが求められます。
今後、事業再生の現場でも、「相続登記の不履行による過料リスク」が一つのリスク管理ポイントとなってくるでしょう。再生計画を立てる際には、登記名義の確認と、相続手続きの状況把握を怠ってはなりません。
最後に──義務化はチャンスにもなりうる
一見、重荷のように思える相続登記の義務化ですが、逆にこれをチャンスと捉えることも可能です。長年放置していた家族間の問題や、見過ごされていた不動産の存在を見直す機会でもあります。利用価値が乏しい土地であっても、近隣と調整すれば境界問題が解決したり、共同売却などの可能性も広がるかもしれません。
制度を知ること、早めに行動すること、そして専門家の力を借りること──この三点が、これからの「相続登記義務化時代」を生き抜くための重要なポイントです。
あなたの家や土地、そして会社の財産に、「登記されていない不動産」はありませんか?
相続登記の義務化は、誰にとっても他人事ではありません。令和9年の期限を前に、今一度、家族で話し合い、必要な対策を講じることを強くおすすめします。
(文:大竹)