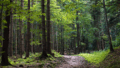2025年上半期、「人手不足」を原因とする中小企業の倒産件数が過去最多となったそうです。東京商工リサーチの調査によると、今年1月~6月における人手不足関連の倒産は172件で、前年同期比で+17.8%の増加。これは2013年の統計開始以来、半年間として最多の記録です。
■ 原因は「求人難」「退職」「人件費高騰」の三重苦
倒産理由の内訳を見ても、
- 求人難:68件(+17.2%)
- 従業員の退職:54件(+31.7%)
- 人件費の高騰:50件(+6.3%)
と、いずれも最多水準です。「待遇改善ができない企業は人手不足に陥り、無理な賃上げをした企業は人件費上昇により資金繰りが悪化する」と言われています。
現場では、「人がいないから回らない」「採ってもすぐ辞める」「賃上げしたら資金繰りが苦しい」といった経営者の声があがっているそうです。
■ 構造的な人材難と“経営判断の麻痺”
例えば、ある製造業では定年退職が相次ぎ、ノウハウの継承ができず生産ラインが半減。新たな人材募集を出しても応募ゼロが続き、受注そのものを断らざるを得ない状態に。
また、飲食業では最低賃金の上昇に合わせて時給を上げたものの、その結果、利益が圧迫されて運転資金が枯渇し、閉店を決断したケースも。
ここで重要なのは、「人手不足=倒産」という単純な構図ではないという点です。
本質的な問題は、刻一刻と変わる経営環境のなかで、“選択肢を持てない状態”に経営者が追い込まれてしまっていることです。
「人が足りない。でも、どうしていいかわからない」
「新しい人を採る余裕もない。残っている社員にもこれ以上負担はかけられない」
「賃上げの流れには乗らなければならないが、それを続ける体力がない」
こうした葛藤の中で、冷静な判断力を失い、選択を“しない”まま時間が経過し、やがて事業が立ち行かなくなる。
この“判断停止”の状態こそが、最も危険なのです。
再生の現場でよく耳にするのは、「もっと早く専門家と相談していれば、手の打ちようがあった」という言葉です。
つまり、人手不足という現象そのものよりも、打開策が見えない状態が倒産の引き金になることが非常に多いのです。
■ 「再生」は“あきらめ”ではなく、“攻め”の選択肢
こうした状況に対し、私たちは「第二会社方式」などの実績ある手法をもとに、再生に向けた具体策をご提案しています。
たとえば赤字部門を切り離し、本業に集中することで、限られた人材と資金を最大限に活かす再構築を実現したケースもあります。
人材難の時代にこそ、「何を守り、何を見直すか」という判断が、再生のカギになります。
「もう人が集まらない」
「賃上げに耐えられない」
そう感じた時こそ、“再スタートの準備”が始まるタイミングかもしれません。
■ 最後に
人手不足による倒産がこれだけ増えているという現実は、特定の業種や規模だけの問題ではありません。
全国的に、そして構造的に広がるこの問題に対し、経営者が孤独に戦い続ける必要はもうないのです。
経営の悩みを、一人きりで抱える時代ではありません。
経営の悩みに寄り添い、再生の道を一緒に探すパートナーとして、私たちは伴走します。「何から始めればいいかわからない」そんな気持ちも、相談のきっかけになります。