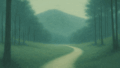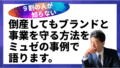中小企業の経営は、理想と現実の間で揺れ動く連続です。
経営理念に忠実でありたい、社員や顧客に誠実でありたいという「清き流れ」を貫きたいという思いは、経営者なら誰しもが抱いているでしょう。
しかし、時にその理想を試すような「濁った流れ」、つまり不本意な判断や苦渋の選択に迫られる場面が訪れます。
資金繰りの悪化は、そうした現実を突きつけてきます。
売上の低迷、支払いサイトのずれ、取引先の倒産、想定外の設備投資や人件費の上昇…。
資金繰りが詰まってくると、「これまで守ってきた美学や信念を曲げてまで、延命を図る意味があるのか」と自問することもあるでしょう。
しかし、そんなときこそ、思い出してほしい言葉があります。
「清濁併呑(せいだくあわせのむ)」
これは、善も悪も分け隔てなく受け入れる度量の大きさを示す言葉です。
澄んだ水も濁った水も、すべて飲み込む大河のように、現実の中にあるあらゆる事象を受け入れ、咀嚼し、自分の糧とする。
そんな姿勢こそが、混迷を極める経営の現場において必要とされているのではないでしょうか。
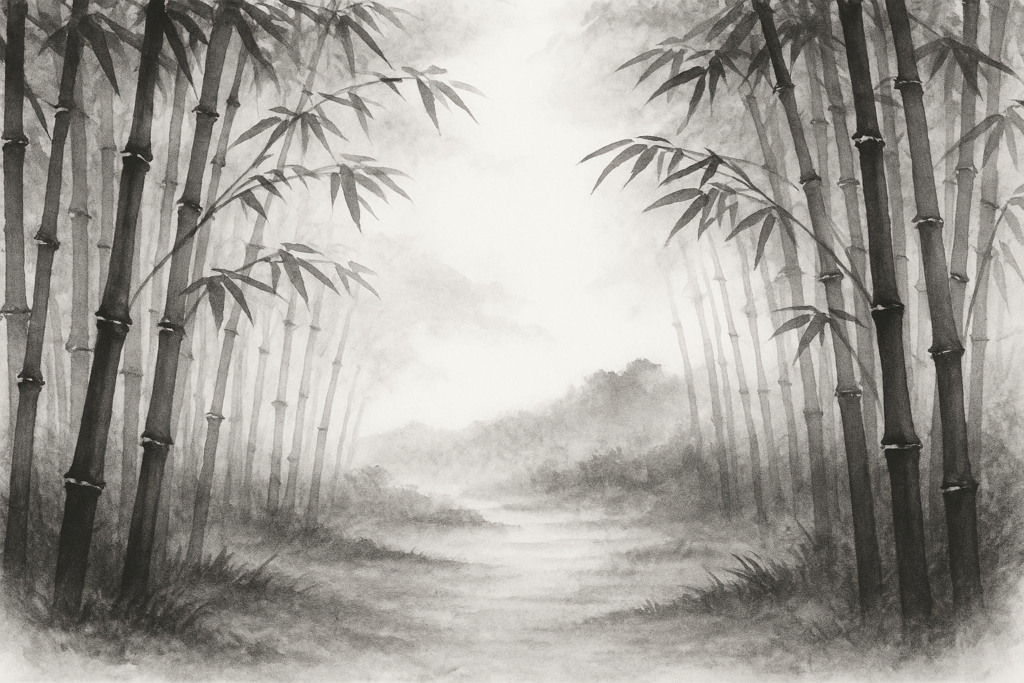
🖊清だけでなく、濁も受け入れる度量
「正しくあること」だけに囚われすぎると、現実への対応が遅れがちになります。
たとえば、業績悪化に気づいていながらも「取引先や社員に心配をかけたくない」「もう少し様子を見たい」という思いから、資金繰り対策を後回しにしてしまうことがあります。
しかし、経営者にとって大切なのは、結果として会社と従業員の生活を守ることです。
融資のリスケジュール、リース料の一時的な支払い猶予、債権者への分割払いの交渉、そして最悪の場合の法的整理など、「きれいごと」だけでは済まない選択肢をも視野に入れなければならないときがあります。
それは決して「悪」ではありません。
むしろ、それを悪と決めつけてしまう自分自身の偏見こそが、経営判断の自由度を奪っていることに気づくべきです。
🖊公平に判断するということ
「清濁併呑」のもうひとつの意味は、「良いことも悪いことも、公平に判断する」ということです。
例えば、過去に助けられた取引先に対して、「苦しいけれど支払いを続けたい」と思う気持ちは自然です。
しかし、資金繰りが尽きれば、結果として全員に迷惑をかけることになります。どこかで冷静な判断が必要になります。
従業員にしても同じです。長く勤めてくれている人には報いたいと思う気持ちは当然です。
しかし、今後の会社の存続を考えたとき、退職勧奨や配置転換、労働条件の見直しといった「濁った選択」をせざるを得ない場面も出てくるでしょう。
そうしたとき、「感情」ではなく「全体最適」の観点から判断する勇気こそが、公平さの根本です。
🖊現実を受け入れる力
多くの経営者が、資金繰りの悪化を「一時的なこと」「なんとかなる」と考え、対応を先送りにしてしまいます。
しかし、本当に現実主義に徹するのであれば、「今ある数字」「今ある現金」「今ある選択肢」から逃げずに直視することが必要です。
現実主義とは、理想を捨てることではありません。
理想に近づくために、まず現実の厳しさを正面から受け止め、乗り越える力を持つということです。
事業再生や資金繰り改善の現場では、「もっと早く相談していれば」という言葉を何度も聞きます。
早期の段階であればあるほど、選択肢は多く、打てる手は広がります。
金融機関とのリスケ交渉、サプライヤーとの調整、補助金・助成金の活用など、使える手立ては意外と多いものです。
ですが、それにはまず、自らの「濁」も含めた経営状況を直視する覚悟が必要なのです。
🖊清濁を併せ呑む経営者こそが、生き残る
現実には、清濁を明確に分けられる場面は少なく、「どちらとも言えないグレーゾーン」の中で、日々判断を迫られるのが経営というものです。
そんな中で、自らの信念や美学にばかりとらわれすぎると、かえって判断が鈍り、対応が遅れ、傷口が広がります。
いま、資金繰りに困っているなら、ぜひ「清濁併呑」の心を持ってください。
経営とは、清らかであることだけを競う場ではありません。
濁った水も受け入れ、それでも前に進もうとする強さと柔軟さが求められるのです。
清流も濁流も、すべてを受け入れて大河となる――その姿こそ、経営者のあるべき姿です。
資金繰りの不安を抱えるあなたも、いま立っているその場所こそが、成長の入り口です。
恥ずかしがる必要はありません。清濁を併せ呑み、現実に向き合い、必要ならば専門家の力も借りてください。
そして、もう一度理想に近づくための「一歩目」を、今日から踏み出してください。
オシリス主任コンサルタント・弁護士・中小企業診断士
大竹夏夫